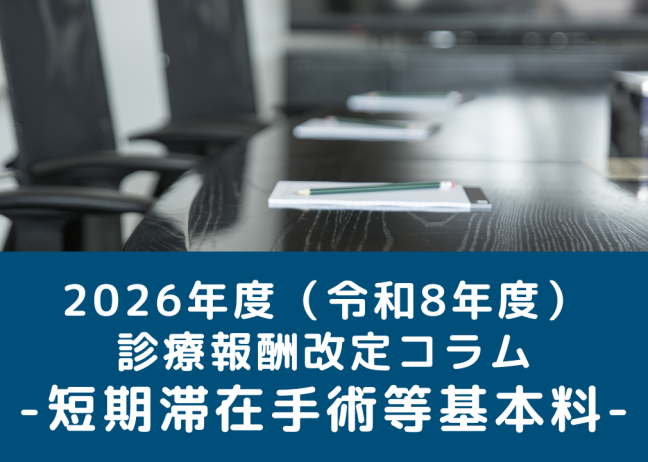
COLUMN
2026年度(令和8年度)診療報酬改定コラム:短期滞在手術等基本料3に関する2026年度診療報酬改定の方向性と病院経営への示唆
2025.12.10
株式会社健康保険医療情報総合研究所
Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)
NEWS
& COLUMNS
COLUMN
2025.10.01
この連載では、「病院情報の公表」における医療の質指標の意味、改善策、そしてデータ分析を通じて事務職員がどのように貢献できるかを解説します。
第1回は、医療安全の重要な指標である「転倒・転落発生率」について取り上げます。
転倒・転落は、患者さんの安全を脅かす身近なインシデントです。特に高齢者や身体機能が低下している患者さんにとっては、骨折や頭部外傷といった重篤な合併症のリスクがあります。
転倒・転落発生率を把握することは、単に件数を数えるだけでなく、院内の安全管理体制がどれくらい機能しているかを評価する上で重要です。
もし、この指標が高い場合は、「病室の環境に問題はないか?」「スタッフの配置は適切か?」「転倒リスクの高い患者さんへのケアは十分か?」など、様々な側面から改善点を探るきっかけとなります。
転倒・転落発生率は、以下の計算式で算出されます。
転倒・転落発生率(‰)=(退院患者に発生した転倒・転落件数 / 退院患者の在院日数の総和) × 1000
転倒・転落発生率を減らすための取り組みは多岐にわたりますが、代表的なものをいくつかご紹介します。
■ 転倒・転落リスク評価の徹底:入院時に、患者さんの過去の転倒歴や身体機能、服用薬などを総合的に評価し、ハイリスクな患者さんを特定します。
■ 安全な環境の整備:ベッドの高さを調節できる電動ベッドの導入、手すりの設置、滑りにくい床材の使用など、物理的な環境を改善します。
■ 多職種連携による介入:医師、看護師、理学療法士、薬剤師など、様々な職種が連携し、患者さん一人ひとりに合わせた転倒予防策を講じます。
さて、ここが病院事務職員の方々に最も知っていただきたいポイントです。転倒・転落発生率の改善に、事務職員はどのように貢献できるでしょうか?
事務職員は、病院運営に関するさまざまなデータを扱うプロフェッショナルとして、データを活用することで医療の質改善に貢献できます。
①指標の「見える化」とトレンド分析
転倒・転落発生率を、月ごと、病棟ごと、時間帯ごとなどにグラフや表にまとめ、「見える化」します。これにより、医療従事者が直感的に現状を把握しやすくなります。
「特定の時期に件数が増えている」「特定の病棟で発生率が高い」といったトレンドを分析することで、改善活動の焦点を絞り込むことができます。
②他のデータとの関連性分析
転倒・転落発生率を、他のデータと組み合わせて分析してみましょう。
○年齢層との関連性:特定の年齢層で発生しやすいか?
○疾患との関連性:どのような疾患を持つ患者さんに多いか?
○入院期間との関連性:入院後何日目に発生しやすいか?
このような分析は、医療従事者がより効果的な対策を立てる上で、重要な情報となります。
③改善活動の効果測定
新しい転倒予防策(例:センサーマットの導入)を導入した場合、導入前と後で転倒・転落発生率がどのように変化したかをデータで示します。これにより、その施策の有効性を客観的に証明できます。
転倒・転落発生率という指標は、単なる数字ではなく、患者さんの安全や医療従事者の努力を可視化するものです。事務職員は、この数字を正確に集計・分析し、そこから見えてくる事実を具体的な改善策につなげる役割を担っています。 次回は「転倒転落によるインシデント影響度分類レベル『3b』以上の発生率」についてお話しします。