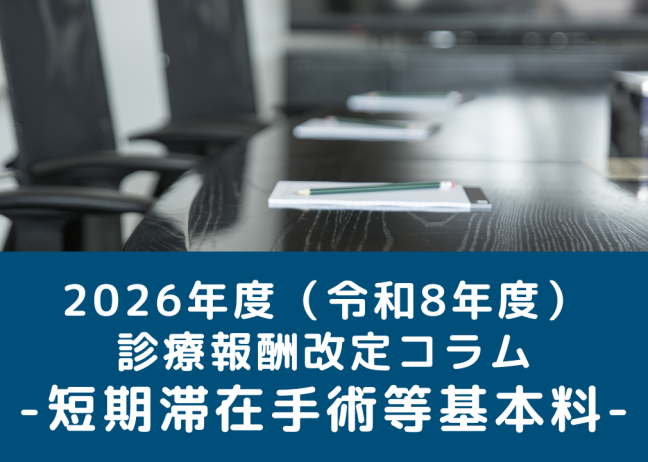
COLUMN
2026年度(令和8年度)診療報酬改定コラム:短期滞在手術等基本料3に関する2026年度診療報酬改定の方向性と病院経営への示唆
2025.12.10
株式会社健康保険医療情報総合研究所
Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)
NEWS
& COLUMNS
COLUMN
2025.10.29
第5回は「広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率」についてお話しします。前回は血液培養についてお話ししましたが、今回は視点を変え、「抗菌薬の適正使用」というテーマを掘り下げます。
「広域スペクトル抗菌薬」とは、さまざまな種類の細菌に効果を発揮する強力な抗菌薬です。重症の感染症や、原因菌が特定できていない場合に、患者さんの命を救うために使用されます。しかし、広域スペクトル抗菌薬を安易に、不必要に使用し続けると、抗菌薬が効かない「耐性菌」が出現するリスクが高まります。
そのため、抗菌薬を投与する前に、必ず原因菌を特定するための細菌培養を実施することが重要です。
この指標が高いということは、原因菌が特定された上で、適切な広域スペクトル抗菌薬が選択されていることを示しています。感染症治療の基本は、原因菌を特定し、その菌に最も効果的な抗菌薬を、必要最小限の期間で投与することです。
しかし、原因菌が不明なまま広域スペクトル抗菌薬を使い続けると、以下のような問題が生じます。
■ 不必要な抗菌薬が投与され、耐性菌出現のリスクが高まる。
■ 本来効果のない抗菌薬を投与し続け、治療が遅れる。
■ 患者さんの腸内細菌叢を乱し、合併症のリスクを高める。
この指標を高めることは、これらの問題を未然に防ぎ、「安全で質の高い感染症治療」を提供する上で不可欠なのです。
この指標は、以下の式で算出されます。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%)=(分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 / 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数) × 100
抗菌薬適正使用のガイドライン策定
感染症治療の専門家(感染制御医師、薬剤師など)が中心となり、広域スペクトル抗菌薬の使用ルールを定めた院内ガイドラインを策定します。「広域スペクトル抗菌薬を処方する前に、細菌培養を必ず実施する」といったルールを明記します。
多職種連携による介入
薬剤師が、細菌培養が実施されていない広域スペクトル抗菌薬の処方箋を発見した場合、医師に「細菌培養の実施」を促します。感染対策チームが、定期的に広域スペクトル抗菌薬の使用状況を監査し、不適切な使用があれば、担当医師に直接フィードバックします。
この指標の改善に寄与し得るデータ分析には、以下のような手法があります。
①処方データと検査データの統合分析
まず、薬剤システムから抽出した抗菌薬の処方データと、検査部門の細菌培養データを統合し、データベースを作成します。そのデータベースを使い、「広域スペクトル抗菌薬が処方されたのに、細菌培養が実施されていない患者」のリストを作成し、医療安全委員会へ提供します。
②「細菌培養未実施」ケースの原因分析
細菌培養が未実施だったケースについて、さらに深く分析します。
「特定の病棟で未実施が多いか?」「特定の診療科で未実施が多いか?」「特定の時間帯に処方された場合に未実施が多いか?」といった視点から分析することで、改善すべきポイントを特定できます。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率という指標は、耐性菌の出現という課題に私たちがどう向き合っているかを示すものです。この指標のデータを正確に集計・分析し、改善に活かしていくことは、患者さんの安全を守ると同時に、未来の医療を守るという重要な役割を担うことにつながります。 次回は「手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率」についてお話しします。