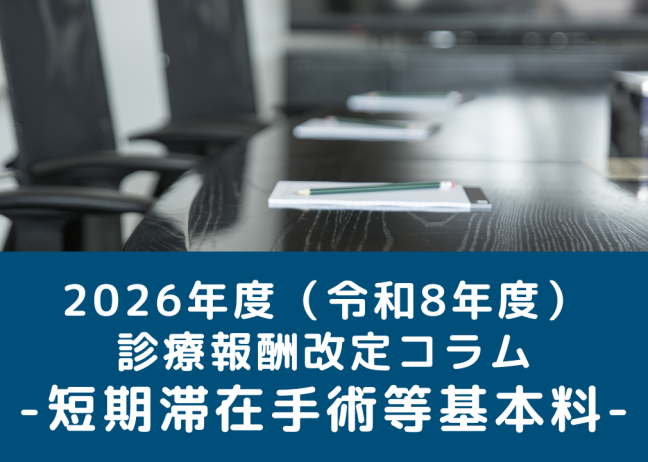
COLUMN
2026年度(令和8年度)診療報酬改定コラム:短期滞在手術等基本料3に関する2026年度診療報酬改定の方向性と病院経営への示唆
2025.12.10
株式会社健康保険医療情報総合研究所
Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)
NEWS
& COLUMNS
COLUMN
2025.11.12
第7回は「『d2(真皮までの損傷)』以上の褥瘡発生率」についてお話しします。
「褥瘡」とは、寝たきりの患者さんなど、同じ体勢で長時間過ごすことで、体の特定の部位に圧迫が加わり、血行不良となって皮膚や組織が壊死してしまう状態のことです。
褥瘡は、患者さんに強い痛みを与え、感染症のリスクを高め、治癒までに長い時間を要することがあります。褥瘡の発生を防ぐことは、患者さんのQOLを守る上で、重要なケアの一つです。
この指標で特に注目するのは、「d2(真皮までの損傷)」以上の褥瘡です。
褥瘡は、その重症度によって段階的に分類されます。
d1(発赤):皮膚の表面に赤みがある状態。適切なケアをすれば比較的早く治ります。
d2(真皮までの損傷):皮膚の表面だけでなく、真皮(表皮の下の層)まで損傷が及んでいる状態。水疱やびらん(ただれ)がみられます。
d3(皮下組織までの損傷):脂肪組織まで損傷が及んでいる状態。
d4(筋・骨への損傷):筋肉や骨まで損傷が及んでいる状態。
このうち、「d2」以上の褥瘡は、適切な体位変換やスキンケアが不十分だったことを示唆する、重症な褥瘡と見なされます。
「褥瘡発生率」という単純な指標では、軽症なd1も含めてしまうため、病院全体のケアの質を正確に評価しにくい場合があります。しかし、「d2」以上の発生率を追跡することで、「未然に防ぐべき重篤な褥瘡がどれだけ発生しているか」を客観的に評価できます。
この指標が低いということは、「褥瘡予防のためのケアが、患者さんの状態に合わせて適切に実施されている」ことを示唆します。
この指標は、以下の式で算出されます。
「d2」以上の褥瘡発生率(%)=(褥瘡(d2真皮までの損傷)以上の褥瘡の発生患者数 / 退院患者の在院日数の総和)× 100
入院時の褥瘡リスク評価の徹底
入院時に、患者さんの褥瘡リスクを評価する「ブレーデンスケール」などのアセスメントツールを活用します。ハイリスクと判断された患者さんに対しては、褥瘡予防計画を立て、個別のケアプランを作成します。
多職種連携による予防策の実施
看護師が中心となって、定期的な体位変換、スキンケア、栄養管理を行います。医師や薬剤師は、褥瘡を悪化させる可能性のある病気や薬のチェックを行います。栄養士は、褥瘡の治癒を促すための栄養指導を行います。
褥瘡ケアチームの設置と活用
褥瘡認定看護師や皮膚・排泄ケア認定看護師が中心となり、医師、薬剤師、栄養士などからなる「褥瘡ケアチーム」を設置します。褥瘡が発生した患者さんや、ハイリスクな患者さんの回診を行い、より専門的な視点からケアを検討します。
この指標の改善に繋がる事務職員の貢献として、以下が挙げられます。
①褥瘡発生データの「見える化」
褥瘡の発生状況をグラフ化し、「見える化」します。「特定の病棟で発生率が高いか?」「入院後どのくらいの期間で発生しやすいか?」「特定の疾患を持つ患者さんに多いか?」といった視点で分析することで、改善すべきポイントを特定できます。
②褥瘡予防用具の導入効果の検証
新しい体圧分散寝具やクッションを導入した場合、データ分析を行い、導入前と後での「d2」以上の褥瘡発生率の変化を数値で示します。これにより、その用具の有効性を客観的に証明できます。
褥瘡予防は、単なる治療行為ではなく、患者さんの苦痛を減らし、尊厳を守るための重要なケアです。褥瘡発生データの集計・分析を通して課題を抽出し、改善につなげることで、患者さんの尊厳を守るという医療の根幹をなす活動に貢献できます。 次回は「65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合」についてお話しします。