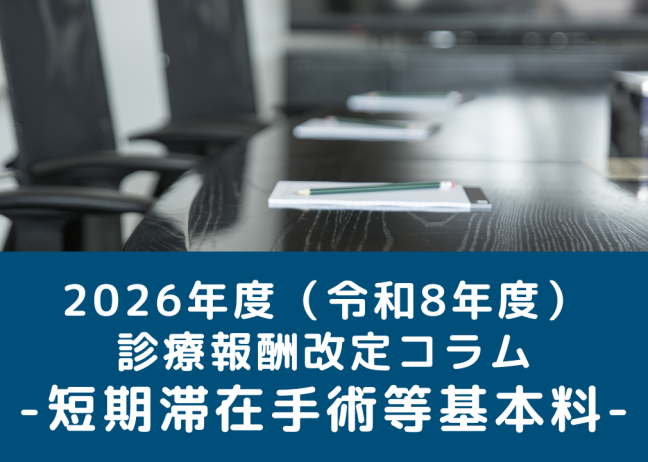
COLUMN
2026年度(令和8年度)診療報酬改定コラム:短期滞在手術等基本料3に関する2026年度診療報酬改定の方向性と病院経営への示唆
2025.12.10
株式会社健康保険医療情報総合研究所
Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)
NEWS
& COLUMNS
COLUMN
2025.10.15
第3回は「リスクレベルが『中』以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率」についてお話しします。
肺血栓塞栓症は、一般的に「エコノミークラス症候群」として知られる病気です。足の静脈にできた血の塊(血栓)が肺の血管に詰まり、呼吸困難や胸の痛みなどを引き起こす、命に関わる合併症です。
特に、手術を受ける患者さんは、長時間の安静や術後の身体活動の低下などから、この肺血栓塞栓症を発症するリスクが高まります。このリスクをいかに予防できるかが、手術の質の高さを測る重要な指標の一つとなるのです。
この指標は、単に「予防策を実施したか」だけでなく、「ハイリスクな患者さんに、適切な予防策がきちんと提供されているか」を評価するものです。
手術を受ける患者さん全員に、同じ予防策を講じる必要はありません。リスクの高い患者さんには、より積極的な予防策を、リスクの低い患者さんには、最低限の予防策を実施することで、医療資源を効率的に使い、かつ患者さんの安全を確保することができます。
この指標が高いということは、リスク評価に基づいた、適切な医療が提供されていることを意味します。
この指標は、以下の式で算出されます。
肺血栓塞栓症の予防対策の実施率(%)= (分母のうち、 肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 / 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数) × 100
予防対策の実施率を高めるためには、医療従事者の連携が不可欠です。
術前のリスク評価と情報共有の徹底
手術前に、患者さんのリスクレベルを正確に評価するためのチェックリストやアセスメントシートを活用します。評価結果は、手術室や病棟の看護師、麻酔科医、そして執刀医間で共有され、予防策の必要性について共通認識を持つようにします。
多職種チームによる予防対策の実施
医師が抗凝固薬の投与を指示し、看護師が弾性ストッキングの着用や間欠的空気圧迫装置の装着を管理します。理学療法士が術後早期の離床や運動指導を行い、血流を促進させます。薬剤師は、患者さんの服用している薬が抗凝固薬の効果に影響しないかをチェックします。
この指標においても、データ分析からわかることがいくつもあります。
①データ集計と分析の自動化
手術の術式や患者さんの合併症情報(DPCデータ)と、予防策の実施記録を組み合わせ、自動的に指標を算出できるシステムを構築します。これにより、定期的なデータ集計の手間を大幅に削減できます。「リスクレベル『中』以上の患者さんで、予防策が未実施だったケース」を自動的に抽出し、リスト化する仕組みを作れば、見落としを防ぐことができます。
②「予防対策が未実施だったケース」の詳細な分析
なぜ予防対策が実施されなかったのか、その原因を究明するために、データ分析を行います。「特定の術式で未実施が多いか?」「特定の医師や麻酔科医の担当時に未実施が多いか?」「週末の手術で未実施が多いか?」といった視点から分析することで、改善すべきポイントを特定できます。
肺血栓塞栓症の予防対策は、患者さんの安全を守るだけでなく、合併症の予防による医療の効率化にも関連する重要な取り組みです。この指標のデータを正確に集計・分析し、改善に活かすことで、医療の質の向上と病院の経営改善という重要な二つの目標を同時に達成することへ繋がります。 次回は「血液培養2セット実施率」についてお話しします。